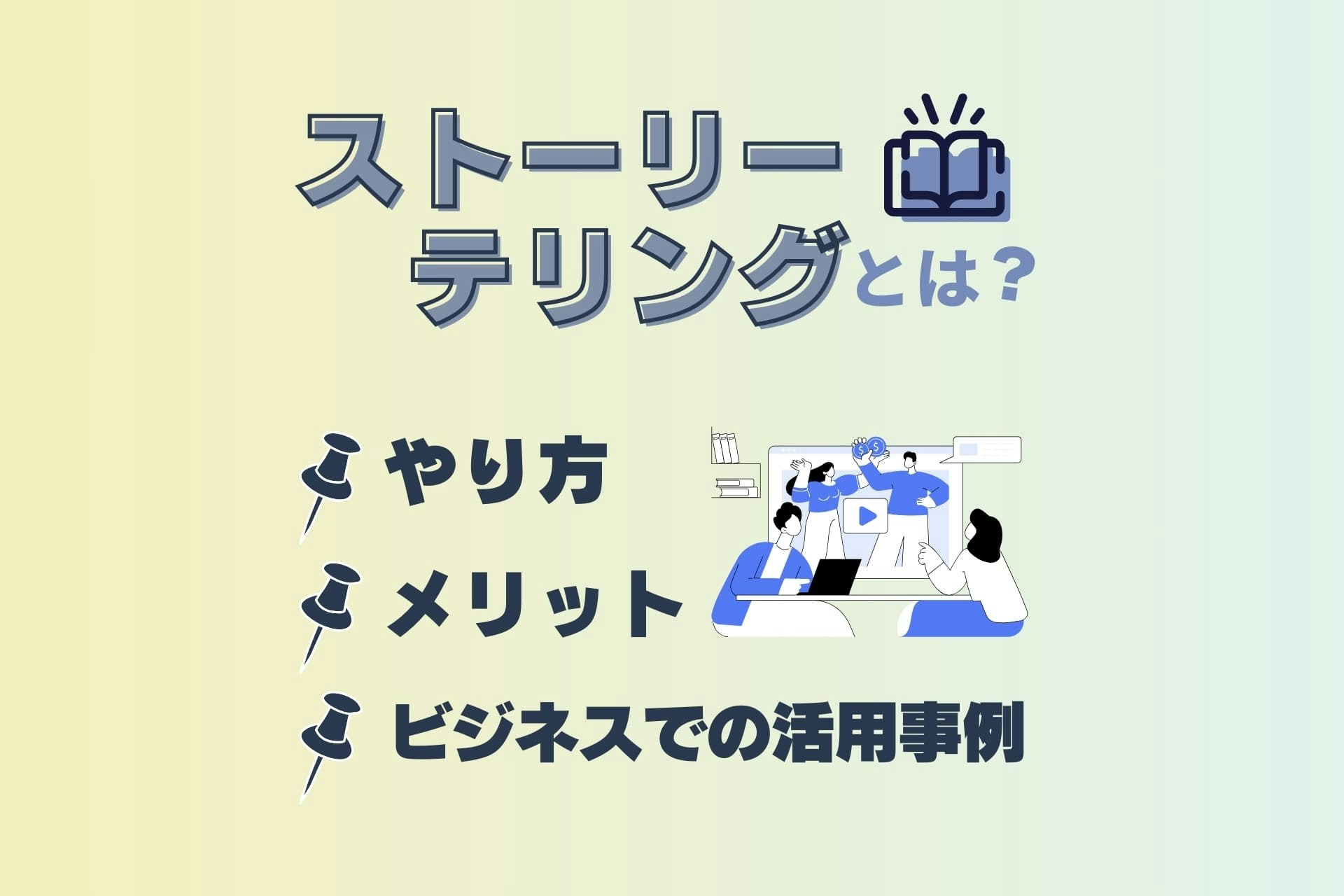ブランディングやプロモーションに携わっている方の中には、ストーリーテリングという言葉を聞いたことがあるものの、「具体的にどのような手法かがわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事ではストーリーテリングの概要や具体例を踏まえつつ、メリットや活用すべき場面などをご紹介します。実施する上での重要なポイントも解説します。
ストーリーテリングとは?
スティーブ・ジョブズが活用したストーリーテリング
レッドブルのCMに見るストーリーテリング
ストーリーテリングの効果・メリット
ストーリーテリングが有効な場面
効果的なストーリーテリングのやり方
まとめ|ストーリーテリングを活用してターゲットに印象づける
ストーリーテリングとは?
ストーリーテリングとは、物語(ストーリー)を活用して自分の主張を相手に理解してもらう手法です。
もともとはアメリカの公共図書館で、子どもに物語を読み聞かせるためのサービスとして生まれ、1960年代に日本に入ってきました。その後ビジネスシーンにおいても着目されるようになったのです。
コミュニケーションを取る際に自分の主張や要望などの要点だけを伝えた場合、聞き手が話の内容をイメージしづらかったり、主張の根拠を信じてもらえなかったりするケースも多くあります。
一方で、ストーリーテリングでは主張したい内容について、前後の流れや背景、実体験などを交えながら物語として語ります。そのため聞き手に深く印象付けることができ、より信憑性が高いと感じてもらえるのです。
自社ブランドについて社内外に発信する際はもちろん、新商品発表などのシーンにおいて、特に有効な手法となるでしょう。
スティーブ・ジョブズが活用したストーリーテリング
ストーリーテリングの活用事例としては、Apple創業者の一人であるスティーブ・ジョブズによる「初代iPodのプレゼンテーション」が有名です。
2001年の初代iPodのプレゼンテーションにおいて、スティーブ・ジョブズは「1,000曲もの音楽が、あなたのポケットに」というストーリーを語ったのです。
MP3メーカーの多くは、プロダクトアウトの発想で機能的な訴求に偏っていました。しかしスティーブ・ジョブズは、先述の短いストーリーによって「iPodを持つことでどのような未来がもたらされるか」をユーザーに思い描かせたのです。
当時ソニーのウォークマンをはじめとして、さまざまなMP3プレイヤーがすでに市場に多く投入されており、iPodは遅れて参入した形でした。それにも関わらず、このストーリーによって多くのユーザーの注目を集め、一躍人気MP3プレイヤーの一つとなったのです。iPodはその後も躍進を続け、2007年には国内市場においてシェア72.4%に達しています。
レッドブルのCMに見るストーリーテリング
エナジードリンクメーカーであるレッドブルは、「Red Bull 翼をさずける」というコンセプトを掲げ、ストーリーを活用したCMを展開しています。
あるCMでは、杖をついた老犬がレッドブルを飲んだ後、スケートボードに乗って深皿型のプールを豪快に一回転します。
エナジードリンクの成分を細かく説明しなくても、このストーリーを見れば、「体力が衰えていても、レッドブルを飲めばパワーがみなぎる」ということが簡単にイメージできるのです。
他にも「レッドブルを飲んだシマウマが、ワニに襲われるも撃退する」といったCMなど、いずれもレッドブルのベネフィットを端的に表現しており、一貫したイメージ訴求に成功している事例といえるでしょう。
ストーリーテリングの効果・メリット
ここでストーリーテリングのもたらす効果を改めて確認しましょう。
イメージしやすく、ターゲットの記憶に残りやすい
ストーリーテリングを活用した主張は、ターゲットの記憶に残りやすいという特長があります。
専門的な用語や数字といった要素は、根拠を示し、信頼を獲得する上で重要な役割を果たします。しかし数字などの細かいデータだけで訴求した場合、ユーザーの記憶に定着させるのは難しいケースもあるでしょう。
一方で、ストーリーを活用すると商品・サービスがもたらす効用をターゲットがイメージしやすいため、効果的に訴求できます。その分、記憶にも残りやすくなり、購買検討を行う際に想起することにつながるのです。
例えば、レッドブルのPRにおいて「○○という成分が○○グラム入っており、これが○○細胞を活性化させることで〜」と伝えても、イメージしづらく記憶にも残りません。
「RedBull 翼をさずける」というメッセージとともに、ストーリーを訴求することで、ターゲットが簡単に商品のもたらす効果をイメージでき、記憶にも定着しやすくなるのです。
iPodの事例でも、「1,000曲もの音楽が、あなたのポケットに」というストーリーをターゲットに伝えることで、iPodが何をもたらすのかを簡単にイメージしてもらうことに成功しています。
共感から信頼を得やすい
ストーリーテリングを用いた主張は共感や信頼を得やすいという利点があります。
単に商品・サービスの機能面だけを訴求しても、ユーザーは自分にとってどのように役立つのかがわかりづらく、共感も覚えにくいといえます。
一方でストーリーの登場人物やその特徴をターゲット像と合わせることで、聞き手に自分ゴトとして捉えてもらうことが可能です。
例えば、先のレッドブルの話でも、老犬は「体力の衰え始めた中高年をイメージした存在」として描写されていることが推察できます。そのため、その世代の視聴者は老犬に自分を重ね合わせてCMを見ることになり、共感を覚えやすいのです。
人間は共感した対象に信頼を置くことが多いため、ストーリーを用いた訴求は信憑性のある情報として受け取られる可能性も高いといえるでしょう。
ストーリーテリングが有効な場面
続いてストーリーテリングが有効な場面について確認します。
ブランディング
ストーリーテリングはブランディングを行う際に役立ちます。ブランドに込められた価値や想いなどをストーリー形式で訴求することで、ユーザーに印象付け、長期的な認知を獲得できるのです。
企業ブランドであれば、創業者がどういう想いで起業したのか、どういった課題を解決したいと考えたのか、といった背景をストーリーとして打ち出すことができます。
商品ブランドであれば、商品開発で技術者がこだわった点や開発に至るまでの経緯、開発段階での印象的なエピソードなどを盛り込むと良いでしょう。
たとえ競合他社が類似する商品・サービスを提供していても、創業の背景や技術者などのこだわりは、差別化ポイントとして機能します。これらの要素を伝えるのに、ストーリーテリングは適しているといえます。
ストーリーテリングを活用してブランドを訴求することで、より深く理解してもらうことができ、顧客のファン化も促せるでしょう。
商品のPR・プレゼンテーション
商品やサービスをPRする上でもストーリーテリングは役立ちます。
商品やサービスを顧客に対してアピールする際、数多くある情報をそれぞれ個別に訴求すると、情報同士の結びつきが理解しづらくなってしまいます。その結果、伝えたい内容が十分に伝わらないケースもあるでしょう。
その点、ストーリーテリングを活用すれば、多数の情報を前後関係などを踏まえた上で整理して訴求できます。また特に印象付けたいエピソードなどをストーリーの中で強調することもできるため、訴求したい内容にポイントを絞って伝えることが可能です。
マーケティング上のコミュニケーションだけでなく、営業におけるプレゼンテーションにストーリーテリングを応用することも効果的でしょう。
商品やサービスが類似していると、営業プレゼンテーションも似たような内容になりがちですが、ストーリーテリングを用いることで、他社とは違う角度でのアプローチができます。アプローチ時点で差別化を実現でき、ターゲット顧客に強い印象を残せるでしょう。
社内教育
ストーリーテリングは対外的なアプローチだけでなく、社内教育にも活用できます。
例えば「○○といったスキルを身に付けよう」と要望だけを伝えても、そのスキルを身に付けて得られるメリットや未来を従業員は想像しにくいといえます。
一方、ストーリーテリングを応用すると、そのスキルを身に付けることでどういった未来が開けるのか従業員が思い描きやすくなります。その結果、従業員のモチベーションを高められ、教育効果も得られやすくなるのです。
また、ストーリーテリングはインナーブランディングにも有効です。
ブランディングでは外部に向けたアウターブランディングとは別に、従業員に対してブランドの浸透や教育を行うインナーブランディングを実施します。この際、ストーリーテリングを用いて内部浸透を図ることで、より深く従業員へのブランドの落とし込みを実現できるでしょう。
会社に所属していることへの誇りや仕事へのやりがいなども感じやすくなり、従業員エンゲージメントの向上といった効果も得られることが期待できます。
効果的なストーリーテリングのやり方
最後に効果的なストーリーテリングのやり方をご紹介します。
ターゲットの明確化
ストーリーテリングを行う場合は、まずどのような特性を持ったユーザーへ語り掛けるのか、ターゲット像を明確にする必要があります。
ストーリーテリングには聞き手の自分ゴト化を促し、共感を得やすいという利点がありますが、ターゲットが曖昧だと効果が弱まってしまうでしょう。
そのためあらかじめターゲットとする聞き手が抱えている課題や悩み、属性などを踏まえて、ペルソナとして明確化しておきましょう。
ここで設定したペルソナを前提にストーリーを作ることで、共感も得やすくなり、訴求力も高まるのです。
データからターゲットの興味・関心を把握
どのようなストーリーを作るかを検討するには、データに基づいてターゲットの興味・関心を把握しなければなりません。
マーケティング担当者の経験や勘など、属人的な判断を参考にペルソナを策定し、そこからストーリーを構築しても、誰にも響かない内容になる可能性が高いでしょう。
そのため、これまでのマーケティングや営業活動を通じて獲得した顧客データを分析し、客観的なデータに基づいて興味や関心事を分析する必要があるのです。
マーケティングオートメーションやCRMといったツールに蓄積されたデータはもちろん、アクセス解析ツールのデータやSNSなどのデータを分析することで、精度を上げることができるでしょう。
経験や勘を排除し、データに基づいて行うPR方法についてより詳しく知りたい方は、こちらのページからガイドブックをダウンロードできるので、ぜひご確認ください。
共感できる内容にする
ストーリーテリングでは、聞き手が共感できる内容にできるかが成否のカギを握ります。
どれほど素晴らしいストーリーを作っても、聞き手が自分ゴト化できなければ、具体的なイメージを持たれることも、強く記憶されることもないでしょう。
ストーリーテリングで効果を上げるには、ペルソナの状況や課題などを深く分析し、共感できる内容を探すことがポイントになります。
ポイントを探し当てた後は、それが適切に聞き手に伝わるように構成を考える必要があります。その際に役立つのがSTAGEの法則です。
STAGEの法則とは
STAGEの法則とは文章作成における型の一つで、以下の5つの要素で文章を構築します。
- Situation:場面
- Trouble:課題
- Action:行動
- Goal:成果
- Epilogue:結び
場面と課題において、ターゲットの自分ゴト化を促す内容を盛り込み、聞き手の興味を引ききます。その後、課題解決のために「どういった行動をしたのか、それによってどのような成果が得られたのか」を話すのです。最後に結びとして、提案や行動喚起などを含めます。
ストーリーを構築する際に何をどこから作ればいいかわからない場合は、STAGEの法則を参考に作成し、実際の活用を通じてブラッシュアップしていくと良いでしょう。
失敗談を語る
STAGEの法則を活用したストーリーを語っても、成功体験などのポジティブな要素しか含まれていない場合、訴求力が弱まるケースがあります。
そういう場合、「Situation:場面」や「Trouble:課題」などの段階に失敗談を盛り込むことで、聞き手からの共感を得やすくなることがあります。
多くの人にとって成功よりも失敗の方が記憶に残りやすいものです。そのため失敗談をストーリーに含めて訴求すると、「自分もそうだった」という共感や親近感を得やすくなるのです。
具体性を持たせる
ストーリーテリングにおいては、具体性も重要なポイントになります。
語っているストーリーが信憑性のあるものとして受け入れられるかどうかは、どれだけ具体的な描写を含められるかにかかっています。
例えば、登場シーンの日付や天気、状況などは細かく描写しましょう。数字的なデータがあれば、「約100万円」といったように大まかに伝えるよりも、「102万円」のように正確な値を伝える方が信憑性が増します。
数字自体を記憶してもらう必要がある場合は、記憶に残りやすいように「約100万円」と伝える方が良いケースがあります。しかし、全体的な物語として訴求したい場合は、具体的な内容を提示しましょう。
まとめ|ストーリーテリングを活用してターゲットに印象づける
ストーリーテリングには、単に商品・サービスを機能的な側面からアピールするよりも、聞き手がイメージをつかみやすく、その記憶にも残りやすいという特長があります。
特にブランディングのように、抽象度の高い内容を伝える際は、ストーリーを使って訴求することで、より深い浸透を図ることができるでしょう。
ただし、ストーリーテリングで効果を出すには、ターゲットを明確にし、データを用いて興味・関心を把握する必要があります。創作や属人的な判断で作ったストーリーでは、誰にも刺さることはないのです。
この記事を参考に、ストーリーテリングによるプロモーションに取り組んで頂ければ幸いです。
この記事の監修者:
宮崎桃(Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター)
国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム